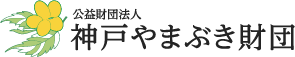[ 奨学生募集についてのよくあるご質問 ]
申込みについて
-
いつから申込みできますか。
2026年度奨学生の募集期間は、2025年9月1日から10月3日まで(当日消印有効)です。書類の不備で再提出していただくケースが発生していますので、期間中早めの申込みをお願いします。
-
申込書類はどこで入手できますか。
- (1)当財団ホームページからダウンロードできます。
-
(2)県内の高等学校、高等部・専攻科のある特別支援学校等および大学等(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校)に募集要項と奨学金給付申込書(様式1~5)をお届けしています。
なお、奨学金給付申込書は、高校時予約奨学生用と大学等在籍者奨学生用の2種類がありますので、確認のうえ選択してください。
-
特別支援学校高等部(本科)の生徒です。「鍼灸師」を目指して、専門学校に行きたいのですが、奨学金の申込みはできますか。
兵庫県内の特別支援学校高等部であれば申込みいただけます。
-
現在、障害者手帳を持っている大学生ですが、申込みできますか。
「大学等在籍者奨学生」に申込みいただけます。
ただし、兵庫県内に実家があり、同県内の高等学校等の高校課程を卒業・修了の後、現在、国内の大学等に在籍し、申込時1~3年生で、経済的援助を必要とする方。
6年制大学の場合、申込時4・5年生も対象です。
障害の等級や年齢の制限がありますので、詳細は募集要項を確認してください。 -
経済的な理由で就学が困難であるとはどういうことですか。
申込者が大学等に進学し卒業するまで修学を継続することが経済的に難しい場合をいい、具体的には申込者の世帯の収入・所得について一定額を上限の目途※としています。 ただし、世帯人数にかかわらず、世帯の年収が1,000万円を超える場合は対象外です。
※4人世帯の場合:年間収入 900万円・年間所得700万円 -
同じ学校、施設、世帯から複数人の申込みはできますか。
学校、施設、世帯とも複数人の申込みは可能です。
原則として学校長および要保護児童の場合は施設長または里親の推薦が必要となります。 -
学校長および施設長(または里親)の推薦とはどういうことですか。
・学校長の推薦
学業・学力、学校内外での活動状況や人物特性など、奨学生として相応しいと思われることについて記入いただきます。 ※大学等に在籍する方は学部長もしくはそれに代わる方に作成を依頼してください。
・施設長・里親の推薦
施設・里親宅での日常生活や日々の活動面に見られる特性・特徴など、奨学生として相応しいと思われることについて記入いただきます。 ※児童養護施設等や里親宅で生活している方が対象です。 -
兵庫県に実家があり、県外の大学等に通学している学生ですが申込みできますか。
兵庫県内に実家があり、原則として同県内の高等学校等を卒業・修了した方は申込みいただけます。
-
申込者本人が申込書を作成(記入等)できない場合はどうすればいいですか。
申込者本人が、障害等により記入できない場合はパソコンによる作成、もしくは代筆でも結構です。
代筆の場合は、申込書の代筆者欄に代筆者名等を記入していただきます。 -
他の団体の奨学金を申し込んでいる(受給する予定がある)が、神戸やまぶき財団の奨学生に申込みできますか。
申込みいただけます。
ただし、受給目的が重複する場合は、支給する金額を調整する場合があります。
当財団の奨学生に採用された時点で、支給額を決定するために、他団体から受給する奨学金の内容(団体名、金額等)を報告していただく必要があります。 -
高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金)との併用について教えてください。
2020年4月から施行された同制度の適用対象となる方(要保護児童および障害者・難病患者で所定の世帯所得の方)は、同制度に申請いただくことを当財団奨学生採用の条件としています。
入学金・授業料の減免額や給付奨学金額に応じて、当財団から支給する奨学金額を一部調整します。 -
通信制大学に進学を考えていますが、申込みできますか。
通信制大学は奨学金支給の対象としていないため、申込みいただけません。
-
大学院に進学を考えていますが申込みできますか。
大学院は奨学金支給の対象としていないため、申込みいただけません。
奨学金について
-
奨学金は、いつ支給されますか。
入学・進級年度の4月から支給を開始します。
入学金等が準備できない方は4月を待たずに支給する場合があります。
詳細は採用内定時(2月上旬)にお知らせします。 -
奨学金で、「実額を支給する」とは、また、「上限額」とはどういうことですか。
実額とは、大学等が発行する納付書等に記載されている実際の納付金額をいいます。
上限額とは、奨学金として支給する金額の限度額のことで、この金額以上は自費になります。
上限額は、入学金は35万円、学資奨学金は年間150万円、生活援助金の通学費は月額3万円、住居費(自宅外通学生)は月額6万円であり、その範囲で奨学金を支給します。 -
奨学金の支給は何年間(いつから、いつまで)ですか。
奨学金の支給は、高校時予約奨学生の場合、大学等への入学から卒業までの期間で、各学校の所定履修期間です。大学等在籍者奨学生は、進級した学年次から卒業までの残りの所定履修期間です。
詳細は募集要項の支給期間をご参照ください。
休学や留年などの場合でも、所定履修期間を超えての支給はしません。 -
専修学校(専門課程)の場合、奨学金は何年間支給されますか。
専修学校では様々な専門課程があり、修得する学科・コースによって履修期間が異なりますが、奨学金の支給期間は、選択した専門課程の学科・コースの所定履修期間で1~4年間の範囲となります。
選考の方法について
-
奨学生としての採用はどのようにして決まりますか。
申込者からの提出書類による第1次審査(書類審査)通過者に対して第2次選考(保護者同席にて面接)を行い、その結果を選考委員会に諮って採用を内定します。
採用内定者が大学等または職業能力開発校等に合格し、入学手続き完了後、あるいは大学等の次学年への進級確定後、これを証する書類を当財団が確認し、申込者から「誓約書」を提出いただくことで、奨学生としての採用を正式に決定します。 -
面接は、いつ、どこで、どのように実施されるのですか。
第1次審査(書類審査)の結果をお知らせするときに、第2次選考(保護者同席にて面接)の対象者には、面接日(11月中旬~12月中旬を予定)と場所(財団事務所を予定)をお知らせします。面接は選考委員が行います。
採用決定後について
-
奨学金はどのように受け取るのですか。
申込者本人名義の金融機関口座へ、振込みにより支給します。
-
奨学金の休止や取消し、返還しなければならない場合がありますか。
奨学生採用後に、奨学生としての重大な義務違反等があった場合、休止や取消しを行い、事情によっては返還していただく場合があります。
-
採用内定後に必要な手続きはどのようにするのですか。
採用内定者には、奨学生の適用区分(支給コース)を書面で通知するとともに、以後の必要な手続きを文書で案内します。
主な手続きとしては、
-
(1)-1.高校時予約奨学生は、大学等または職業能力開発校等の合格通知書を当財団に提出していただきます。
財団は合格確認後、申込者と推薦人に正式採用決定を通知します。また、申込者には各コースに準じた必要書類を個別に案内します。 -
(1)-2.大学等在籍者奨学生は、大学等の次学年以降の進級決定を示す書面等と授業料納付通知書の写しを当財団に提出していただきます。
財団は次の学年への進級を確認後、申込者と推薦人に正式採用決定を通知します。また、申込者には各コースに準じた必要書類を個別に案内します。 -
(2)正式採用通知を受けた日から10日以内に誓約書他(財団所定様式)を提出していただきます。
財団は提出いただいた書類を確認後、個々に応じた奨学金を算定し、結果を通知します。 -
(3)算定結果である「奨学金給付通知書」をご確認後、受領書を提出していただきます。
財団は「奨学金給付通知受領書」を確認後、4月以降、奨学金を支給します。
-
(1)-1.高校時予約奨学生は、大学等または職業能力開発校等の合格通知書を当財団に提出していただきます。